社員に対して研修会開催の案内を行うための重要な社内文書です。効果的な研修実施のためには、参加者の理解と積極的な参加を促す分かりやすく魅力的な案内が不可欠です。研修の目的・内容・効果を明確に伝え、参加者のモチベーション向上と確実な参加を実現します。会員登録不要・無料ですぐにテンプレートをダウンロードしてご利用できます。
書き方の基本ポイント
必須記載事項の体系化
研修の基本情報
- 研修名・テーマ:具体的で魅力的な研修タイトル
- 目的・狙い:なぜこの研修が必要なのかの明確な説明
- 対象者:参加すべき社員の範囲と選定理由
- 期待効果:研修参加により得られる具体的なメリット
開催詳細情報
- 日時:開催日・時間・所要時間の詳細
- 会場・形式:開催場所・オンライン/オフラインの形式
- 講師・ファシリテーター:専門性と信頼性のアピール
- 定員・参加条件:参加者数の制限や前提条件
参加に関する実務情報
- 申込方法・期限:具体的な申込手順と締切日
- 準備事項:事前学習・持参物・システム準備等
- 費用・予算:参加費用や会社負担の範囲
- フォローアップ:研修後の活用・評価・継続学習
研修種類別の案内ポイント
スキルアップ研修
- 業務に直結する実践的なスキル向上
- 受講前後の能力比較・測定方法
- 現場での活用事例・成功事例
- キャリア開発への具体的な貢献
コンプライアンス研修
- 法的義務・リスク管理の重要性
- 違反事例・社会的影響の説明
- 社内規程・ガイドラインとの関連
- 全員参加の必要性と義務
マネジメント研修
- 対象者の役職・責任範囲との関連
- 組織運営・人材育成への効果
- リーダーシップ発揮の具体的場面
- 部下育成・チーム力向上への貢献
新技術・DX研修
- 業界動向・競合他社の状況
- 業務効率化・生産性向上の効果
- 導入予定システム・ツールとの関連
- 将来のキャリア・スキル要件
参加意欲を高める表現技法
緊急性・重要性の訴求
- 「業界の急激な変化に対応するため」
- 「新制度施行に伴う義務研修として」
- 「競合他社に先駆けた取り組みとして」
- 「お客様からの要望・期待に応えるため」
具体的メリットの提示
- 「業務効率が平均30%向上します」
- 「新しい資格取得・認定につながります」
- 「昇進・昇格の要件を満たします」
- 「最新のツール・手法を習得できます」
限定性・希少性の演出
- 「年1回の貴重な機会です」
- 「外部講師による特別セミナー」
- 「先着○名限定での開催」
- 「今回限りの特別プログラム」
具体的な記入例
良い例(DXスキル向上研修)
令和7年7月15日
社員各位
代表取締役社長 田中太郎
人事部長 佐藤花子
令和7年度「DXスキル向上研修」開催のお知らせ
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は業務にお励みいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、デジタル技術の急速な進歩により、あらゆる業界で
DX(デジタルトランスフォーメーション)への対応が
企業の競争力を左右する重要な要素となっております。
弊社におきましても、お客様により良いサービスを提供し、
業務効率の向上と働き方改革を実現するため、
全社員のDXスキル向上を戦略的重要課題と位置付けております。
つきましては、下記の通り社員研修会を開催いたしますので、
該当する社員は必ずご参加ください。
【研修概要】
■研修名
「実践で活かすDXスキル向上研修
~AIツール活用とデータ分析の基礎~」
■研修の目的・背景
1. 急速に普及するAIツールの業務活用スキル習得
2. データドリブンな意思決定能力の向上
3. 業務プロセスのデジタル化・自動化の推進
4. お客様のデジタル需要への対応力強化
■期待される効果
・日常業務の効率化(平均30%の時間短縮目標)
・データに基づく提案力・企画力の向上
・新規事業・サービス開発への貢献
・キャリアアップ・スキル向上による評価向上
【開催詳細】
■対象者
・営業部・企画部・システム部の全社員(必須参加)
・その他部署で希望する社員(任意参加)
・管理職・マネージャー(部下育成のため推奨)
■日程・会場
・第1回:令和7年8月10日(土)9:00-17:00
会場:本社3階会議室A・B
・第2回:令和7年8月17日(土)9:00-17:00
会場:本社3階会議室A・B
※2回とも同内容です。いずれか1回にご参加ください
※オンライン参加も可能(Zoom使用)
■定員
・各回30名(先着順)
・オンライン参加:各回20名
【プログラム内容】
■午前の部(9:00-12:00)
「AIツール活用の実践」
・ChatGPT、Copilot等の業務活用法
・文書作成・データ分析の効率化
・プロンプト作成のコツと注意点
■午後の部(13:00-17:00)
「データ分析とビジュアライゼーション」
・Excel・Power BIを使った分析手法
・効果的なグラフ・ダッシュボード作成
・データに基づく提案書作成演習
【講師紹介】
■メイン講師
山田一郎氏(DXコンサルタント)
・○○大学情報学部教授
・大手IT企業でのDX推進責任者経験15年
・「実践DX入門」(○○出版)著者
・経済産業省DX推進アドバイザー
■サブ講師
弊社システム部長 鈴木次郎
・社内DX推進チームリーダー
・実際の業務改善事例を基にした実践指導
【参加申込・準備事項】
■申込方法
・社内ポータルサイトの専用フォームから申込
・申込期限:令和7年7月31日(水)17:00
・先着順のため、お早めにお申し込みください
■事前準備
・ノートパソコン持参(社用・私用問わず)
・Microsoft Office(Excel必須、Power BI推奨)
・Zoom アプリ(オンライン参加の場合)
・事前学習動画視聴(申込者に別途案内)
■当日の持参物
・ノートパソコン
・筆記用具
・名刺(グループワーク用)
・昼食(社員食堂利用可)
【研修費用・支援制度】
■参加費用
・受講料:無料(会社全額負担)
・交通費:通常通り支給
・昼食代:各自負担(社員食堂割引適用)
■資格取得支援
・研修修了者には「DXスキル認定証」を発行
・外部資格(マイクロソフト認定資格等)取得支援
・受験料・更新料の会社負担制度あり
【研修後のフォローアップ】
■実践サポート
・研修後1ヶ月間の質問サポート(専用チャット)
・月1回のフォローアップセミナー開催
・社内での実践事例共有会
■評価・キャリア反映
・研修成果を人事評価に反映
・DXプロジェクトへの優先アサイン
・社内講師・メンター制度への参加機会
【注意事項・お願い】
■参加時の注意
・遅刻・早退は原則禁止
・グループワークのため積極的な参加をお願いします
・研修内容の録音・録画は禁止
・SNS等での内容公開は控えてください
■緊急連絡先
・人事部研修担当:田中(内線1234)
・システム部サポート:山田(内線5678)
・当日緊急連絡:080-1234-5678
【今後の展開】
本研修は、弊社DX推進戦略の第一段階として位置付けており、
今後以下の展開を予定しております:
・第2弾:AI活用プロジェクト実践研修(11月予定)
・第3弾:デジタルマーケティング研修(来年2月予定)
・社内DX推進チーム結成と実践プロジェクト開始
この研修を通じて、全社員のDXスキル向上を図り、
より効率的で創造的な働き方を実現してまいります。
積極的なご参加をお待ちしております。
ご不明な点がございましたら、人事部までお気軽に
お問い合わせください。
以上悪い例
研修を行います。
日時:○月○日
場所:会議室
対象:全員
参加してください。研修種類別の記入例
新入社員研修
【研修の背景・目的】
新入社員の皆様が一日も早く職場に適応し、
弊社の一員として活躍していただくため、
ビジネスマナーから実務スキルまで
幅広く学んでいただく機会を設けました。
【特徴・メリット】
・同期との絆を深めるチームビルディング
・先輩社員によるメンター制度
・実際の業務を想定したロールプレイング
・3ヶ月後の成長実感を測定・フィードバック管理職研修
【研修の必要性】
昨今の働き方改革、多様な人材活用、DX推進等により、
管理職に求められる役割・スキルが大きく変化しています。
現代の管理職として必要な知識・能力を習得し、
より効果的なマネジメントを実現していただきます。
【対象者の選定理由】
・現在管理職の方:マネジメントスキルの再確認・向上
・管理職候補の方:昇進・昇格の前準備として
・プロジェクトリーダーの方:チーム運営力の強化コンプライアンス研修
【研修の重要性・緊急性】
昨年施行された個人情報保護法改正により、
企業の責任がより厳格化されました。
違反した場合の社会的信用失墜、顧客離れ、
法的責任等のリスクを回避するため、
全社員の正しい理解と実践が不可欠です。
【参加の義務化について】
本研修は法的要求事項を満たすための必須研修です。
参加できない場合は、別日程での受講または
e-ラーニングでの補完受講が必要となります。法的・実務的な留意点
労働法・就業規則との関係
研修参加の義務化
- 業務命令としての研修参加義務
- 勤務時間内・外での開催の取り扱い
- 参加拒否・欠席時の対応・処分
- 合理的配慮(障害者・妊娠中等)
労働時間・賃金の取り扱い
- 研修時間の労働時間該当性
- 休日・時間外研修の割増賃金
- 交通費・宿泊費等の実費負担
- 資格取得費用の会社負担・返還義務
人事評価・処遇への反映
- 研修参加・成果の評価への反映
- 昇進・昇格要件としての位置づけ
- 不参加・低評価時の処遇への影響
- 公平性・透明性の確保
個人情報・プライバシー保護
参加者情報の管理
- 参加者名簿・連絡先の適切な管理
- 研修記録・評価結果の保護
- 第三者(講師・業者)への情報提供
- 写真・動画撮影時の同意取得
研修内容の機密保持
- 企業機密情報の取り扱い
- 参加者間での情報共有ルール
- SNS・外部での情報発信制限
- 研修資料の複製・持ち出し制限
安全配慮義務・リスク管理
会場・設備の安全確保
- 会場の安全性・バリアフリー対応
- 感染症対策・衛生管理
- 緊急時の避難経路・連絡体制
- 障害者・高齢者への配慮
オンライン研修の注意点
- システムトラブル時の対応
- 個人端末使用時のセキュリティ
- 通信環境・技術サポート
- 著作権・肖像権の保護
使用タイミングと注意事項
年間研修計画との連携
計画的な研修実施
- 年度初めの研修計画策定・公表
- 四半期・月次での実施スケジュール
- 他部署・他研修との重複回避
- 繁忙期・イベント等との調整
タイムリーな研修実施
- 法改正・制度変更への迅速対応
- 新技術・トレンドへの即応
- 組織変更・新サービス開始時の対応
- 問題発生・改善必要時の緊急実施
効果的な案内タイミング
事前周知期間の設定
- 1ヶ月前:研修計画の概要発表
- 2週間前:詳細案内・申込開始
- 1週間前:最終確認・リマインド
- 前日:当日の注意事項・準備確認
申込・準備期間の確保
- 十分な検討・調整時間の提供
- 事前学習・準備作業の時間確保
- システム・機器準備の時間考慮
- 代替要員・業務調整の時間配慮
よくある失敗例と対策
失敗例1:参加対象者が不明確
- 問題:「関係者」「該当者」等の曖昧な表現
- 改善:具体的な部署名・役職・条件の明記
- 対策:参加者リストの事前作成・確認
失敗例2:研修の目的・メリットが不明
- 問題:「スキルアップのため」等の抽象的表現
- 改善:具体的な業務改善効果・キャリアメリット
- 対策:過去の研修効果・参加者の声の活用
失敗例3:実務情報が不足・不正確
- 問題:会場・時間・準備物等の詳細不足
- 改善:詳細な実務情報と確認方法の提供
- 対策:複数部署での情報確認・検証
失敗例4:一方的な通知で参加意欲が低い
- 問題:命令的・強制的な表現のみ
- 改善:参加メリット・期待効果の積極的アピール
- 対策:参加者の自主性・意欲を尊重した表現
よくある質問(FAQ)
Q1: 研修参加を義務化できる法的根拠は? A1: 労働契約に基づく業務命令として、業務遂行に必要な研修への参加を義務化できます。ただし、合理性・必要性があり、労働者の不利益が過度でないことが条件です。
Q2: 休日・時間外研修の賃金支払い義務は? A2: 業務命令による研修は労働時間に該当し、休日・時間外の場合は割増賃金の支払いが必要です。任意参加の場合は労働時間に該当しない場合もあります。
Q3: 研修不参加者への処分は可能か? A3: 正当な理由なく業務命令としての研修を欠席した場合、懲戒処分の対象となり得ます。ただし、処分は合理的で相当なものである必要があります。
Q4: 外部講師・業者への個人情報提供は問題ないか? A4: 研修実施に必要な範囲での個人情報提供は可能ですが、事前の同意取得や機密保持契約の締結が必要です。最小限の情報提供に留めてください。
Q5: オンライン研修での著作権侵害リスクは? A5: 研修資料・講義内容の無断録画・録音・共有は著作権侵害となる可能性があります。事前の注意喚起と適切な利用ルールの設定が重要です。
Q6: 研修効果が上がらない場合の対策は? A6: 参加者のニーズ調査、研修内容・方法の見直し、事前・事後学習の強化、実践機会の提供、上司・組織のサポート体制強化等を検討してください。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。ファイル形式はWord(ワード)です。
重要な注意事項:研修案内は単なる事務連絡ではなく、社員の学習意欲を喚起し、組織全体の能力向上を図る重要なコミュニケーションツールです。参加者の立場に立った分かりやすく魅力的な内容、実務に直結する価値ある研修の企画・実施、継続的な学習・成長を支援する仕組みづくりが重要です。
-e1673662786574.jpg)
-e1673662786574-1477x1536-1673662831.jpg)
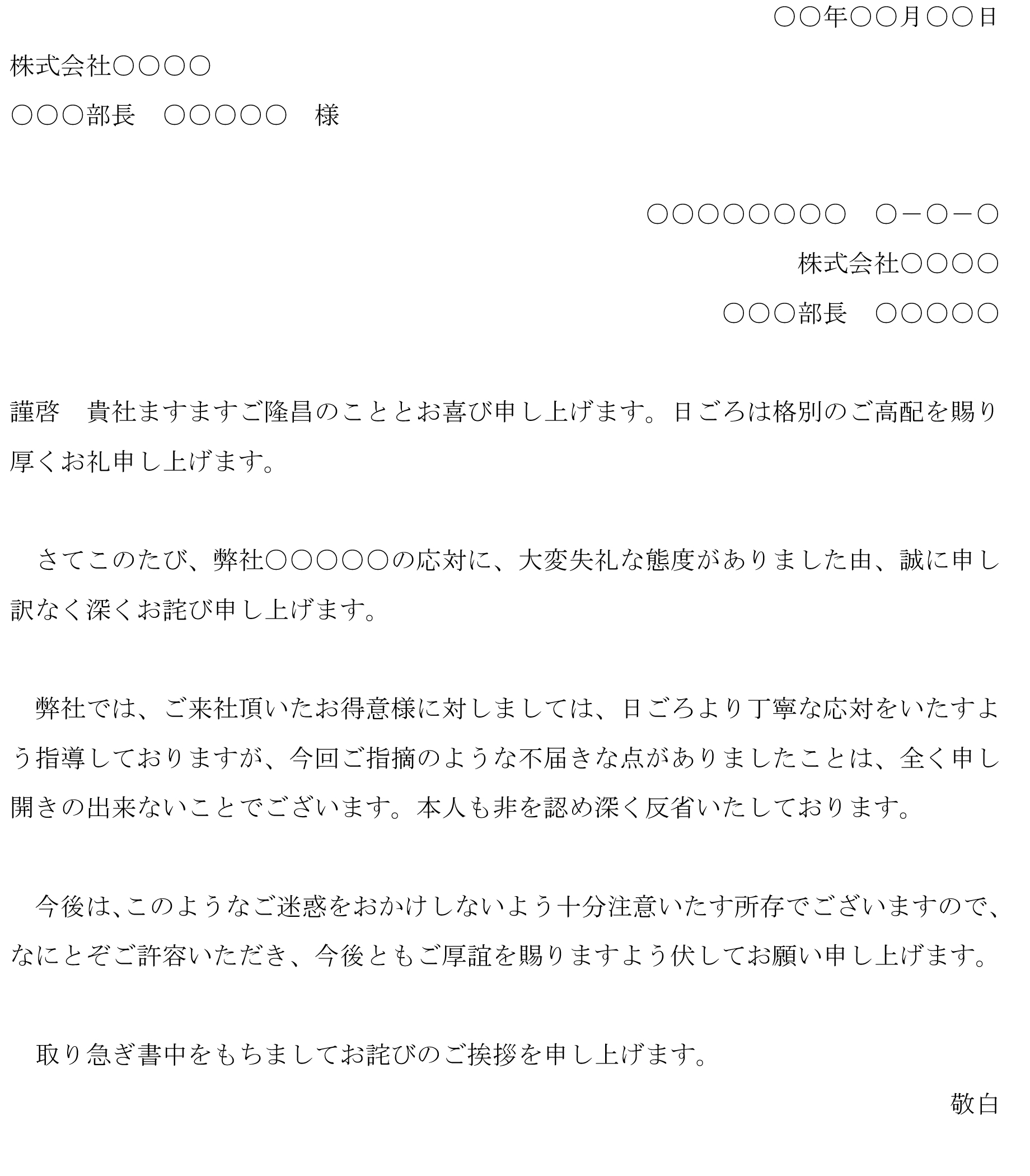
-e1673663068677.jpg)